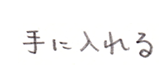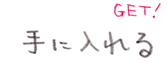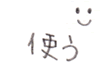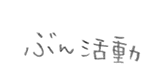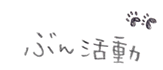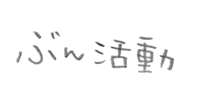ぶんぶんウォーク2012 スロータウン『地域通貨シンポジウム』
「地域通貨、はじめませんか。」
第一部「エンデの遺言」上映会
第二部「カフェからはじまる地域通貨」パネルトーク

河邑厚徳
『エンデの遺言』ディレクター 1948年生まれ。東京大学法学部卒業。映画監督、元NHKディレクター・プロデューサー。女子美術大学教授。現代史、芸術、科学、宗教などを切り口に数々のドキュメンタリーを制作。『がん宣告』『シルクロード』『アインシュタインロマン』『チベット死者の書』『エンデの遺言~根源からお金を問うこと~』など著書も多数。
1948年生まれ。東京大学法学部卒業。映画監督、元NHKディレクター・プロデューサー。女子美術大学教授。現代史、芸術、科学、宗教などを切り口に数々のドキュメンタリーを制作。『がん宣告』『シルクロード』『アインシュタインロマン』『チベット死者の書』『エンデの遺言~根源からお金を問うこと~』など著書も多数。
吉岡淳
スロータウン総合監督 (有)カフェスロー代表取締役。30年間にわたるユネスコ運動を経て、2001年東京都府中市にスロー・ムーブメントの拠点となる「カフェスロー」をオープン。以後「スローカフェ」の普及と人材育成にとりくむ。大学やカルチャーセンターで講師をつとめる。
(有)カフェスロー代表取締役。30年間にわたるユネスコ運動を経て、2001年東京都府中市にスロー・ムーブメントの拠点となる「カフェスロー」をオープン。以後「スローカフェ」の普及と人材育成にとりくむ。大学やカルチャーセンターで講師をつとめる。
高浜洋平
水の学校・おたカフェ 1977年生まれ。大学で都市計画を学び、建設会社にて都市開発に携わる。休日には国分寺の地域づくりに取組み、東京経済大学国分寺市地域連携推進協議会研究員、お鷹の道おもてなし事業実行委員。2009年「史跡の駅おたカフェ」や「水の学校」立上げに携わる。
1977年生まれ。大学で都市計画を学び、建設会社にて都市開発に携わる。休日には国分寺の地域づくりに取組み、東京経済大学国分寺市地域連携推進協議会研究員、お鷹の道おもてなし事業実行委員。2009年「史跡の駅おたカフェ」や「水の学校」立上げに携わる。
影山知明
進行役・クルミドコーヒー店主 1973年西国分寺生まれ。外資系コンサルティング会社勤務、ベンチャーキャピタ リストを経て、2008年、生家の地にこどもたちのためのカフェ「クルミドコー ヒー」 を開業。開かれたコミュニティづくりに取り組む。
1973年西国分寺生まれ。外資系コンサルティング会社勤務、ベンチャーキャピタ リストを経て、2008年、生家の地にこどもたちのためのカフェ「クルミドコー ヒー」 を開業。開かれたコミュニティづくりに取り組む。
地域通貨シンポジウム①
第1部 河邑厚徳さん 影山知明さん対談
影山さん:![]() 個人的にはようやくお会いできたという感じでして。『エンデの遺言』が放送された当時に拝見し、第一印象として「なんだこれは!」と思ったことをよく覚えています。ハンマーで頭を殴られたような。お金とか経済に対する常識を「本当にそうなの?」と問いかけるような番組で、それ以来『エンデの遺言』『エンデの警鐘』と読んでいます。
個人的にはようやくお会いできたという感じでして。『エンデの遺言』が放送された当時に拝見し、第一印象として「なんだこれは!」と思ったことをよく覚えています。ハンマーで頭を殴られたような。お金とか経済に対する常識を「本当にそうなの?」と問いかけるような番組で、それ以来『エンデの遺言』『エンデの警鐘』と読んでいます。
この番組を制作された当時のことあたりから少しお聞きしたいと思うんですが。
河邑さんがこの番組をそもそもお作りになろうと思った経緯は、どんなことだったんでしょうか。
河邑さん:![]() そもそもの話になるんですが、その当時ミヒャエル・エンデと出会って5,6年経ってました。最初に取材を申し込んで話を聞いたのは『アインシュタインロマン』というNHKスペシャルの企画で、エンデにはそのスペシャル番組の案内役をお願いしたんです。それはなぜかというのは、すごく単純なんですけど、アルバート・アインシュタインがドイツ人。それで同じドイツ人の、ミヒャエル・エンデを。
そもそもの話になるんですが、その当時ミヒャエル・エンデと出会って5,6年経ってました。最初に取材を申し込んで話を聞いたのは『アインシュタインロマン』というNHKスペシャルの企画で、エンデにはそのスペシャル番組の案内役をお願いしたんです。それはなぜかというのは、すごく単純なんですけど、アルバート・アインシュタインがドイツ人。それで同じドイツ人の、ミヒャエル・エンデを。
ミヒャエル・エンデは、『モモ』で時間をテーマに本を書いていました。一方アインシュタインの最も大きな仕事は「相対性理論」。相対性理論も時間と空間についての一つの新しい発見なんです。「時間」を挟んで、一方では芸術家であり作家であるミヒャエル・エンデの思想を、もう一方に科学者であるアインシュタインの思想をぶつけたら、いわゆる理系と文系と言われますが、それを超えた大きな一種の知の新しい地平が開けるのではないかなという発想があって。それでミヒャエル・エンデにその番組への参加を依頼しました。
最初、ミヒャエル・エンデは非常に慎重で、断られてしまいました。「自分は自分のことをよくわかってないし、そんなところに自分がしゃしゃり出て話すのは、とても僭越だし嫌なんだ」と。
その「嫌なんだ」っていう言葉なんですが、皆さんアインシュタインというものを神格化してるでしょ。「アインシュタインのことを、みなさんは天才の一人として肯定的にしか捉えていない。だけど、僕はそうじゃない。アインシュタイン個人ということではないが、自然科学について、科学というものは実はまだ非常に未熟なものなんだ」と。
「結局、科学というものは客観性。対象を計測して、観測して、操作したりする学問。でも、本来人間の本質には目に見えない、形では捉えられない精神・心・一種のスピリチュアルのようなものがあるんだ。それをまったく、科学というものは放棄している。そっちの部分は宗教に任せればいいと言っているが、それは全く違う。
科学が本当に真の科学になれば、つまり科学の進歩があれば、そういうトータルなものを扱えるようになるんだ。そういう批判的なことを僕は言うけどいいのかい?」と言われて、まさにそれが望んでいたことです、と。
最初僕は、アインシュタイン神話から抜け出していなかったのですが、ミヒャエル・エンデの話を聞くうちに、そんな風に変わってきました。そういう形でのミヒャエル・エンデとの出会いがありました。
その延長線上で、実は最後に「アインシュタインの企画は終わったけれど、実は僕が一番やりたいことが残ってる。それを、ぜひ映像化できないか。」という提案を受け、それで、今映像の最初の方にテープがあったと思うんですけど、あのテープを録音したところで、まさにミヒャエル・エンデは病気で亡くなったんですね。
僕としては、テープ1本で番組を作るのはほとんど不可能だと思って、4,5年は何もしなかったんです。でもそのうちやっぱり、今の市場経済、グローバリゼーションの中で、アジアの国々がめちゃくちゃに…。様々な光景がありましたけれど、経済がどんどんどんどん暴走し始めて、世界中がおかしくなってるって実感があって。
「そうか、ミヒャエル・エンデが本当にやりたかったことは、こういうことだったんだな。それをちゃんとやらないと、ミヒャエル・エンデに応えることにならない」と思い、あのテープを基に構成したのが、この『エンデの遺言』です。まさに遺言になったと思うのですが。ちょっと長くなってごめんなさい。
影山さん:![]() いえいえ。
いえいえ。
亡くなられたのが95年で、番組が放映されたのが99年でしたよね。その放送から13年経っているわけなんですけれども。
この間のことをお聞きしていきたいのですが、『エンデの遺言』が放映されて以降、こういう言葉が適切かどうか分かりませんが、「地域通貨ブーム」というものが起こってたように思うんです。日本各地で地域通貨の取り組みがあり、逆に言うとそれだけのインパクトがこの番組にあったということだと思うんですが、残念ながら続かないものも現れ、あるいはまた挑戦するものも現れ、サイクルを続けているように思います。その13年間については、今、河邑さんからご覧になって、どんなふうに捉えていらっしゃいますか。
河邑さん:![]() やっぱり放送直後から、圧倒的に地域通貨に対してみんな関心を持ってくれて、「もしかしたら、地域通貨が一種の閉塞状況を打破する切り札になるんじゃないか」という少し過大な期待を持って、「わが地域でやろう」「わが仲間内でやろう」という話が結構ありました。
やっぱり放送直後から、圧倒的に地域通貨に対してみんな関心を持ってくれて、「もしかしたら、地域通貨が一種の閉塞状況を打破する切り札になるんじゃないか」という少し過大な期待を持って、「わが地域でやろう」「わが仲間内でやろう」という話が結構ありました。
ただミヒャエル・エンデが一番言いたかったことは、地域通貨のムーブメントというのは、一つの処方箋にすぎない。ミヒャエル・エンデが一番問題にしたのは、「システム」という言葉を使っていますが、それは今のグローバル経済、金融至上主義ということなんです。
ですから、我々が自明のものとして生きている現代社会の一番根幹にあるお金のしくみというものをもっと相対化して、お金に支配されるのではなく、自分たちがよりよい社会を作るためにお金を使う方法を早く人類は身につけるべきだ、という中の一つに地域通貨があったんです。
多分そういう意味では、ミヒャエル・エンデが一番問題にしたのは利子の問題だと思います。
利子の問題については、今も専門の経済学者が扱っているテーマですが、よく考えると利子があってモノが増えているということは、自然界にはないんですね。有限であり、持続可能な状態というのが、生態系のバランスがとれている生きていく姿なんですが、一方的にあるモノだけが増えているということは、多分自然界にはない。
それは、あるとすれば、お金の増殖。
自然界のものはすべてある時間の中で、劣化したり、腐ったり、命が無くなったりする。人間もそうですね。有限な存在ですから、有限な存在の、本来等価物である。物々交換の代わりにお金が発明されたわけだから、有限なものと無限なものを交換し始めては。
お金を否定すべきではありませんが、そういう意味で地域通貨というのは万能ではない。ある地域に限定されている。ただし、今の行き過ぎた市場経済のマネーに対しての、ある小さなカウンターにはなるのでは、ということなんですね。
僕は今、ぎっくり腰にあまり薬が効かなくて、鍼とお灸でやってますけど、どっちかというと地域通貨もそういうもんだと思っています、経済に対して。いきなり目に見えて、薬を飲んだら、ぱっと世の中が変わっている魔法のようなものではなくて。地域通貨にもし意味があるとしたら、気長に、あんまりあせらず、こう何か楽しんで使っていくような一つの道具であるという風になれば、きっと続くかなぁという気がしますね。
影山さん:![]() 利子が利子を呼んでいるという、無限に自己増殖を続けていくマネー経済というか、実体経済から切り離された構造なんかもあるかと思うんですが。
利子が利子を呼んでいるという、無限に自己増殖を続けていくマネー経済というか、実体経済から切り離された構造なんかもあるかと思うんですが。
個人的な話をさせていただきますと、実は私、もともと投資ファンドの仕事をしていまして。まさに、金融資本主義の申し子といいますか、それは冗談にしましても、それに近い仕事をしていたんです。逆にそういった仕事をしていた分だけ、こういうことに魅かれてきているということもありまして。
というのも、ベンチャー企業に投資をして、その支援をするわけですが、その会社がこれからどのように経営のかじ取りをするかという時に、当然色んな分岐点があるんです。
たとえば、創業の頃の想いに忠実にやりたいことを実現していく。あるいはこれを実現すればきっと喜んでくれる人がいる、でも残念ながらあまり儲かりませんという選択肢A。一方、選択肢Bはすごく儲かる。でも元々やりたかったことではないし、誰が喜んでくれるのかもよくわかりません。その時に、じゃあどっちを選ぶかという話になるんですね。
当然、なんとなくAを選びたいという感じが少なくとも個人的にはあるんですが、職業人としての自分は、Bを選べと言わざるを得ない。「売り上げを伸ばせ」「利益を増やせ」と。
それは、僕自身の気持ちというより、僕が投資家との間で行っている契約があるからなんです。増やして返すという約束をしている以上、増やさなくてはいけない、ということを負う。このメカニズムっていうものを僕は小さな中に体験したんですけれど、社会全体でそれが行われているということなんじゃないかと思ったんです。
誰もそれを望んでいないのに、みんながなぜかお金のために動く・お金のために働くというような社会経済システムになってしまっているシステムの力学の怖さを自分で体験して、それでこっちに帰ってきたという経緯があったわけなんです。
河邑さん:![]() それは素晴らしいですね。おそらく一生その魔法が取れないために、すごくがんばって仕事をしている人がいると思うんです。
それは素晴らしいですね。おそらく一生その魔法が取れないために、すごくがんばって仕事をしている人がいると思うんです。
さっき申し上げたように、有限な世界の中であるモノだけが成長していったとしたら、その成長の代償を払うのは当たり前のことです。
その一つが環境で、その成長の代償として環境が損なわれていく。もう一つは貧富の格差。一部の非常に豊かな国と、ますます本当に日常水もない・食糧もないという国がまずます増えている。本来、イスラム諸国とかアフリカとか、南アメリカとか多様でそれぞれの文化があって、決して優劣をつけがたく、幸せで人と人とのつながりもあって、豊かな暮らしをしてきた国々が地球上にはたくさんあったんですよ。
でも、ある種価値を数字に置き換えた瞬間に、一つの規準から優劣がどんどん広がっていく。
利子というのは、借りた方には負債がどんどん増えていきます。貸した方は、利子が増えていくから、リターンも増えていく。利子という小さなものを考えただけでも、格差がどんどん増える構造になっている。
当たり前すぎる話なのに、専門家はそういうことを指摘しない。大学の経済学者、経済が専門の政治家、企業人もそう。企業というのは、自分たちが成り立たなくてはならないので、いろんな努力をして可能な方向に向かっていると思うけど、アカデミズムや政治というのは旧来のシステムに囚われたままだという気がどうしてもしちゃうんですね。
影山さん:![]() 時代的に言うと、『エンデの遺言』が放映された20世紀後半の頃とそれ以降の13年間に、河邑さんをはじめとして色んな方が「このままの経済でいいのか」という問題提起をされてきているように思うんです。
時代的に言うと、『エンデの遺言』が放映された20世紀後半の頃とそれ以降の13年間に、河邑さんをはじめとして色んな方が「このままの経済でいいのか」という問題提起をされてきているように思うんです。
実際にその間バブルもはじけて、経済的にも景気が悪い時期が続いていく中で、もう少しみんなが「これからの社会経済というのはこういう方向なんじゃないか」と声をあげるようなことがあってもよかったように思うんです。
すごくシンプルな聞き方で語弊があるかもしれませんが、『エンデの遺言』が放映された99年当時と今の2012年を比べてみて、どちらがいい状況だと思われますか。
人間は、少しは学んだのでしょうか?
河邑さん:![]() 一般の生活者やごく普通の市民にとって、20世紀の終わりは、やはり経済成長の記憶もあり、日本がどんどん右肩上がりになっていた。そういうことが強くあったので、今影山さんがおっしゃった問題提起についても、わかってはいたけど、実感というか、本当に自分のものにはなっていなかったんじゃないかな。
一般の生活者やごく普通の市民にとって、20世紀の終わりは、やはり経済成長の記憶もあり、日本がどんどん右肩上がりになっていた。そういうことが強くあったので、今影山さんがおっしゃった問題提起についても、わかってはいたけど、実感というか、本当に自分のものにはなっていなかったんじゃないかな。
でも、今は「これ何とかしようよ」って考えている人がすごく増えてきていると思います。
何と言っても圧倒的に、3.11後に「この社会では(やっていくことが)できないぞ」とみんなが基本的には考えはじめている。なのに、政治の場や大きな企業・大学を中心とした、これまで原子力エネルギーを推進してきた人たちだけが旧来のまま。周りはどんどん変わっているのだから、もう確実にこのままではやっていけないし、時代は変わっていく。そういうことがどんどん増えてきていると思いますけどね。
影山さん:![]() 確かにそういう感じがしていますね。じゃあ実際これからどういう社会・どういう経済を作っていくかということになったとき、はたと、なかなかイメージがわかないと言いますか、どっちに足を踏み出していいのかという感覚もあるように思うんです。
確かにそういう感じがしていますね。じゃあ実際これからどういう社会・どういう経済を作っていくかということになったとき、はたと、なかなかイメージがわかないと言いますか、どっちに足を踏み出していいのかという感覚もあるように思うんです。
これから先を見通したときに、少なくともこういうこと大事にやっていけば状況がよくなっていくんじゃないかと思われていることって、なんかありますか。
河邑さん:![]() 僕は学者でもないし、ジャーナリストとして取材をとおしていろいろなものを見てきたにすぎないんですけど。僕が一番思ったのは、ここが文明の転換点だとすると、
僕は学者でもないし、ジャーナリストとして取材をとおしていろいろなものを見てきたにすぎないんですけど。僕が一番思ったのは、ここが文明の転換点だとすると、
(背後にある『国分寺のスローな未来を描くシンポジウム』という横断幕を指さして)
「スローな未来って何なんだろう」ということを皆で共有するのが一番近いのかなと思っているんです。
「スロー」っていう概念は「時間」のことでしょ。スローに対してファスト。
おそらく18世紀から19世紀・20世紀に世界中で行われてきたことの一つは「唯一の基準」をつくること。たとえば時間でいうと「グリニッジ標準時」で世界中を覆い尽くすこと。そして、それぞれの国では神話や文化を背景にしていろいろな暦があったはずだけど、それを「西暦」が覆い尽くした。
経済のシステムはできるだけ障壁をなくして、構造改革した。小泉さんの構造改革なんかがそうだけど。それぞれの国の間を自由にモノ・ヒト・カネが行き来するのがグローバリゼーションで、よりよき人類の未来につながるという考え方。
そこにお金の唯一の基準がつくられる。それはドルですよ。それからEUROも。それぞれの国が色んな通貨を持っていたけど、EUROという共通のお金をつくってしまった。
グリニッジ標準時とコンピューターのwindowsソフト、ドルとEUROと西暦と。
その方向って何に向かっているのか。要するに世界中の多様性がなくなるわけですよね。世界中の多様性や歴史や文化よりも、そういうひとつの基準を選ぶことで非常に経済が効率化する。ややこしいことが無くなっちゃう。
この、ある一つの基準でこの地球を覆いつくすという方向に対して、もし対抗軸があるとしたら、小さな多様性だと思うんです。地域通貨もそうなんだけど。
時間が早く過ぎることが人にとっての幸福とか社会の進歩というわけではない。時間を本来の人間の時間に取り戻そう。
そのようなことを、僕は大きな枠組みでは考えていて、それが今作っている『天のしずく』にもつながっている。そういうことになるんですけど。
ちょっと質問の答えになってなかったですかね。
影山さん:![]() いえ。ちょうど『天のしずく』のお話も聞こうと思っていたんですけれど。
いえ。ちょうど『天のしずく』のお話も聞こうと思っていたんですけれど。
今のお話は、小さな多様性というお話ですよね。
世界唯一の基準に動かされることによって、それが効率的ではあっても個のヒダヒダみたいなものは失われ均一化していく。そういうことに対して、小さな多様性というものをどう作っていくか。
今回『食』と言うテーマで映画を作られていますよね。「小さな台所の風景」という表現とか、小さいことの大切さを描かれている。「ごく当たり前の平凡な日常の中にある、とても深い非凡」という表現もされていました。
これまで本などを拝見していて、経済や社会のこれからのシステムということを語られてきている河邑さんが、とてもミクロな、ピンポイントな所にフォーカスを当て始めているというところが、すごく印象に残ったんですけども。そのあたりは、どんな思いでいらっしゃるんでしょうか。
河邑さん:![]() 年を取ったんじゃないですかね。
年を取ったんじゃないですかね。
影山さん:![]() いえいえ笑。そういう部分もある。そういったこともある、に加えて
いえいえ笑。そういう部分もある。そういったこともある、に加えて
河邑さん:![]() 人間が生きているということをよく考えると、生きているというのは食べ続けているということで。生きることと食べることというのは、まったく同じなんですよね。
人間が生きているということをよく考えると、生きているというのは食べ続けているということで。生きることと食べることというのは、まったく同じなんですよね。
「生きること」に戻ってきたときに、この「時間」に戻ってくるんですよ。生きるっていうのは、日常のささやかな行為の積み重ねでしょ。1人ひとりが自分だけの時間のなかで日々生きているわけじゃないですか。自分の時間のものさしで。
モモのテーマは、その「時間」。時間を節約するという言い方で、時間に利子をつけて今むちゃくちゃ働いて、それを老後に3倍にして楽しもうという、一種の詭弁みたいな話がでてきますが、それって本当っぽいけど、でも人生ってそれだけじゃないでしょ?だから時間を取り戻す。
スローにも時間概念があるし、市場経済もいかに早くいかに効率的にということを念頭に置いている。しかも企業だと必ず1年ごとに決算があって時間の漆黒なかでいろいろな結果を出そうとする。そこに入っている人間が、自分の時間を全部そこに注ぎこんじゃう。するとどんどん自分がなくなっちゃう。そんな気がするんですね。
『天のしずく』で言うと、「日本人の忘れもの」というキーワードを思いついたんですけれど。
明治時代の日本は、すごく遅れてきた国が西洋の近代化で必死に走ってきて。そういうことを繰り返してきて、今のわたしたちの暮らし方となっているんですよね。
でも幸福感を持っているのかとか、人と人とのつながりがちゃんと結ばれているのか、教育の場で何が起きているのかとか考えると、いろんなことがどこかでつながっている。
さしあたっては自分の時間っていうものを、自分に取り戻すにはどうしたらいいのかと考える。
その中にライフスタイル、地域通貨、家族との時間の過ごし方ということも含まれてくる。
時間というと、アインシュタインに戻っちゃうんですけど。
ニュートンが、「自然科学がやってきた時間と人間の時間は違う」と。
やっぱりモモのテーマに戻ってきちゃう気がして、ミヒャエル・エンデは僕の生涯の先生だなと思います。
影山さん:![]() これは私事なのですが、中学時代に『モモ』を読んで読書感想文を書きまして。愛知県で賞をいただいたりなんかしまして。非常に思い入れの深い1冊なんです。
これは私事なのですが、中学時代に『モモ』を読んで読書感想文を書きまして。愛知県で賞をいただいたりなんかしまして。非常に思い入れの深い1冊なんです。
もう一つ、『果てしない物語』には、「ファンタージェン」と「虚無」という言葉が出てきます。
大きなしくみのなかでお金や、自分の外側にある目的のための自分の存在となると、自分の存在がどんどん薄っぺらくなって来る。つまり自分の時間が失われていくということですよね。この状況のことを、おそらく彼は「虚無」という言葉で語っていた。
それに対抗しうるものがあるとしたら「ファンタージェン」、「想像力」というんでしょうか。小さなファンタジーのようなものが、虚無に対して力を持ちうる最後の砦になるんじゃないかと、この作品は言ってくれているんじゃないかと個人的には思いまして。
そういう角度からも、僕にとっても思い入れの深い一冊なのですが。
そんな経緯で今日河邑さんにお会いできたというのも、とてもうれしいんですけども。
河邑さん:![]() エンデの弟子2人ですね。
エンデの弟子2人ですね。
影山さん:![]() そうですね。ある意味そういう対談になっていますね。
そうですね。ある意味そういう対談になっていますね。
(河邑さん・影山さんの対談はおしまい。トークセッションへ続く)